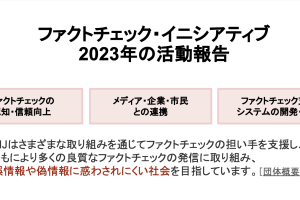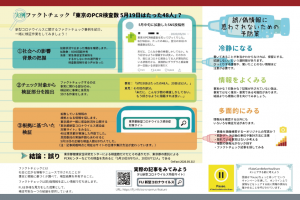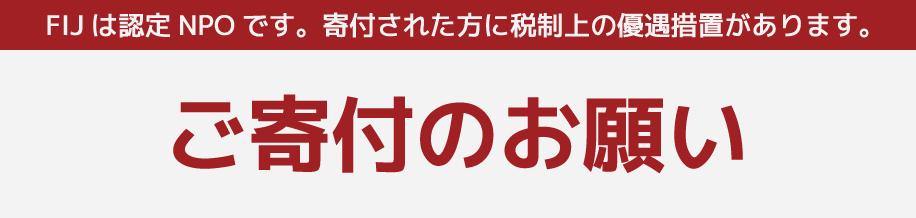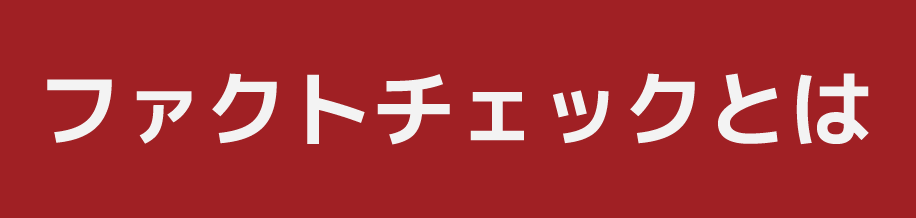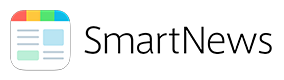2025年7月の参議院選挙において、複数の政党が、自党に関係するSNS上の真偽不明の情報に対して「ファクトチェック」の取り組みをすることを明らかにしました[i][ii][iii]。また、同年9月に自民党が公表した参院選総括報告書[iv]においても、「ファクトチェックやBot対策等により、正確な情報を届ける」ことが今後の取り組みとして掲げられました。こうした動きの背景には、偽・誤情報の拡散が有権者の判断を歪めることになり、民主主義の基盤を揺るがしかねないという危機感があると考えられます。その危機感は共有しますが、その際に使われる「ファクトチェック」という語は国際的に確立した原則に沿って用いられるべきであると考えています。
そのため、政党による「ファクトチェック」という言葉遣いは、国際的に確立した原則に基づく「ファクトチェック」とは異なることに注意する必要があります。
FIJは、ファクトチェック推進・支援団体として、「ファクトチェック」という言葉が誤解されないよう、以下のとおり見解を表明します。
自民党の報告書に「平時からファクトチェック」
自民党の参院選総括報告書は、「ファクトチェック」の項目において、さらに具体的に「野党の主張や、ネット上で拡散するデマ・誤情報に対応するため、平時からファクトチェックを行い、具体的なデータを示した反証・訂正情報を公式サイトやSNSで発信する体制を整備する」と記しています。政党が、自党に関する言説を調査して反証・反論することは、表現の自由の一環として認められる言論活動ですが、国際的に確立された、第三者による「ファクトチェック」とは明確に区別すべきです。
ファクトチェックに求められる独立性
FIJは、広く国際的に認知されている国際ファクトチェック・ネットワーク(IFCN=International Fact-Checking Network)のファクトチェック綱領[v]の趣旨を踏まえて、具体的なファクトチェック・ガイドラインを作成しています[vi]。その中で、ファクトチェックを次のように定義しました。
公開された言説のうち、客観的に検証可能な事実について言及した事項に限定して真実性・正確性を検証し、その結果を発表する営み。
そのファクトチェックに取り組む際には、IFCNのファクトチェック綱領に記された5つの原則を遵守する必要があります。IFCNの原則は以下の5つです。
・非党派性と公正性
・情報源の基準と透明性
・資金源と組織の透明性
・検証方法の基準と透明性
・オープンで誠実な訂正方針
このうち第一の原則である「非党派性と公正性」は、ファクトチェックが特定の政治勢力から独立して行われることを求めています。具体的な要件の一つに「いかなる政党、政治家、または政治候補者とも提携しない」ことを挙げています。
また、欧州ファクトチェック基準ネットワーク(EFCSN=European Fact-Checking Standards Network)も独自のファクトチェック綱領[vii]を用意しています。倫理的な原則の冒頭に「非党派性と公平性」が挙げられており、その細則には、ファクトチェック組織の要件として、以下の記述があります。
・編集上の自由と政治的独立性を有すること
・政党や政府、または政党・政府の直接管理下にある公的企業において、給与を得ている者や重要な地位にある者を雇用しないこと
EFCSNは、IFCNよりさらに明確に、政党から独立した第三者によるファクトチェックを原則としていることが分かります。
FIJの基本的立場
FIJは、国際的な原則などに照らして、ファクトチェックは本来、当事者や利害関係者ではなく、党派から独立した第三者が行うべきものであると考えています。政党が自らに関する言説を検証することを、「ファクトチェック」と称することは、国際的定義に照らせば、誤用といえます。
また、政党は与党・野党を問わず、権力の「予備軍」であり、その判断には必然的に党派的視点が入り込むため、「非党派性」や「公正性」を満たすことは極めて困難です。さらに、権力を持つ、あるいは将来的に持つ可能性のある政党が「ファクトチェック」を名乗ることは、結果として言論弾圧や検閲の口実となるおそれがあります。
そのため、党派的活動に用いることは控える必要があると考えます。
政党による情報発信のあり方
政党が、自らの立場や政策に関する情報に対して根拠を示して反論することは、民主的な言論空間に資する行為と言えます。その場合、「公式見解」や「反論声明」といった表現を用いれば、国際的に確立された、第三者によるファクトチェックとの混同を避け、政党の考えを伝えることができます。
そうした「公式見解」や「反論声明」を、独立した報道機関やファクトチェック団体に提供し、第三者によるファクトチェックの結果を尊重する姿勢が求められます。
もちろん、「公式見解」や「反論声明」においても、その透明性を確保するため、検証プロセスや根拠資料を可能な限り公開し、恣意的な情報選別との疑念を市民に与えないよう配慮することが重要です。
<注>
[i] 「安野貴博氏代表の「チームみらい」 「ファクトチェック用AI」を開発」https://mainichi.jp/articles/20250526/k00/00m/040/152000c
[ii] 「公明、SNS上でファクトチェック AI活用、6月上旬から」https://www.jiji.com/jc/article?k=2025053000945&g=pol
[iii] 国民民主党 第27回参議院議員通常選挙特設サイト 政党ファクトチェックhttps://election2025.new-kokumin.jp/factcheck/
[iv] 自民党 第27回参議院議員通常選挙総括委員会報告書「国民政党としての再生に向けて」https://storage2.jimin.jp/pdf/news/information/211343_1.pdf
[v] International Fact-Checking Network, Code of Principles. https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/the-commitments
[vi] ファクトチェック・イニシアティブ, FIJのガイドラインhttps://fij.info/introduction/guideline
[vii] European Fact-Checking Standards Network, Code of Standards. https://efcsn.com/code-of-standards/
修正:脚注[iii]を追記しました。(2025.9.16)