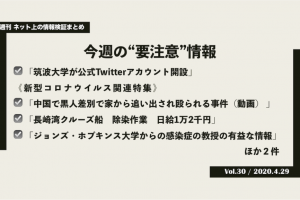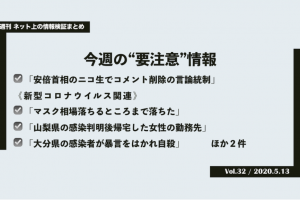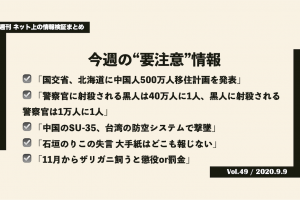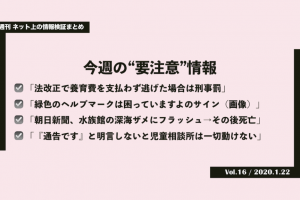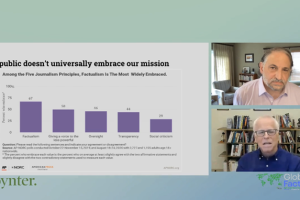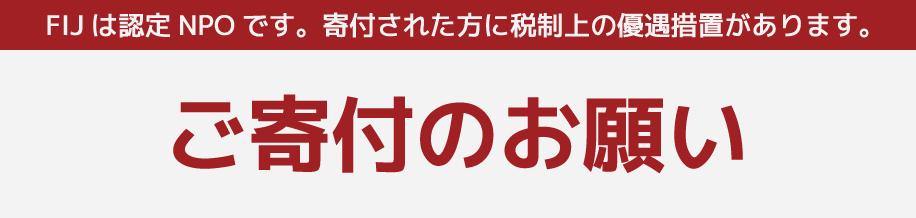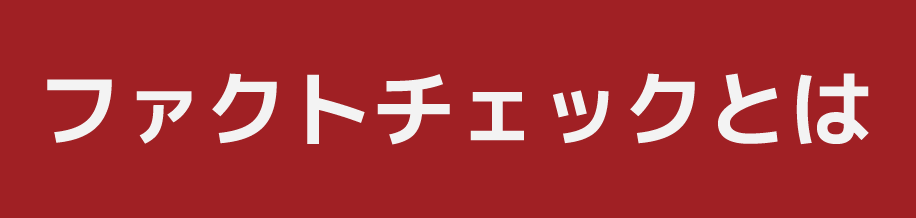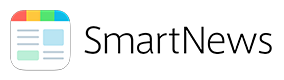ワシントンポストのトランプ大統領に対するファクトチェックの業績は、権力の監視というジャーナリズムの機能を果たす検証記事について、さまざまなモデルを提供する価値あるものです。これは本文中で説明する2018年9月7日付のファクトチェック記事(記事トップのスクリーンショットを筆者撮影)
※この記事はYahoo!ニュースエキスパートに掲載されたものを、筆者が一部加筆修正して転載するものです。Yahoo!ニュース編集部のご厚意にこの場を借りて感謝を申し上げます。
(文中敬称略)
ファクトチェックをめぐる2つの「誤解」を解く(その1)〜「オンライン」だけが強調されてはいけない に続いて、日本でもやっと本格的になってきたファクトチェックが、効果的なジャーナリズムの一部として定着するために、必要なことを議論しています。
②ファクトチェックとは、格式ばったものではなくて、社会に深刻な悪影響が蔓延する恐れがあるのなら、柔軟に対応しなければならない。
「意見はファクトチェックしない」という原則
各社が「ファクトチェックとは何か」という説明を公開しています。その中で「ファクトチェックの対象」となる言説について、「意見はチェックしない」「オピニオンチェックではない」という記述がみられます。
朝日新聞社 ファクトチェックの指針(2025年6月13日)
【2】ファクトチェックの対象
検証の対象となるのは、「意見(オピニオン)」ではなく、公開された言説・情報のうち、検証可能な「事実(ファクト)」の部分です。
対象は、個人・企業・団体などによる、発言・文章・画像・映像など、公に発信されたあらゆる言説・情報を含みます。また、発信した主体が特定できない場合でも、広く拡散され、社会的な影響が大きいと判断した場合は検証の対象とします。
対象とする言説・情報は、影響する範囲の大きさや、影響の深刻さなどを考慮して選定します。
ファクトチェックとは? 情報が「事実」かどうかを検証(読売新聞 2025年6月18日)
個人の意見や思想信条は対象外
有志社が行うファクトチェックは情報に含まれる「事実」が正確であるか否かを検証するもので、個人の意見や思想信条は対象になりません。
例えば、同じ人物についての言説でも、「伊藤博文は日本の初代首相である」という言説は事実かどうかの検証が可能なので対象になりますが、「伊藤博文は偉大な首相である」は個人の主観に基づく「意見」なので対象としては適当ではありません。
ファクトチェック、手法は?基準は?(毎日新聞 2019年6月30日)
また、チェック対象とするのは、社会に広く流布した真偽が定かでない言説や情報です。意見や主義主張ではなく、客観的に検証ができるものについて、公益性や社会的関心の高さなどを考慮して選んでいます。
大手メディアの何社かが依拠している、JFC(日本ファクトチェックセンター)でも以下のような説明があります。
ファクトチェックとは 定義・ルール・手法を解説(2024年1月29日)
「オピニオンチェック」ではない
重要な点は「事実を検証すること」です。意見を検証(オピニオンチェック)するわけではありません。
民主主義社会の日本では、憲法19条が思想及び良心の自由を、憲法21条が言論や表現の自由を保障しています。だからと言って、嘘やねじ曲げられた「事実」が広がって、誤解や誤った判断につながれば、個人の生活や社会を不安定にします。
事実と意見を切り分ける
意見ではなく事実を検証するとはどういうか。「雲が出ている。雨が降りそうだ。傘を持とう」という言説があるとして、どこが検証対象となる「事実」なのかを考えてみます。
この場合、提示されている事実は「雲が出ている」です。「雨が降りそうだ」は雲が出ていることを前提とした上での推測であり、「傘を持とう」は雨が降りそうだという推測を元にした判断です。(後略)
政治の言説はもっと複雑
ファクトチェックは最大限、論理的でなければならないはずです。そのためには言説を裏付ける「エビデンス(証拠)」が必要です。
したがって、感想や、個人的な想いの反映としての意見は検証ができませんし、「ファクトチェック」という名目の下で、自由な意見の表明を妨げることは、あってはなりません。各社の説明や定義はもっともなことだと思います。
しかし、政治の世界で飛び交う言説は、もっとあいまいで、複雑で、巧妙なものです。硬直した「意見はファクトチェックできない」という考え方は、時にファクトチェックやジャーナリズムの機能を弱めてしまうこともあり得ると思われます。
ワシントンポストが挑んだこと
アメリカのワシントンポストに有名なファクトチェッカーのグレン・ケスラーという名物記者がいます。
トランプ大統領の1期目には7人のファクトチェックチームを率いて、彼が発したすべての発言をファクトチェックし、3万件以上のウソやミスリードな点を指摘、現在もトランプ大統領に対するファクトチェックを続けています。

ワシントンポストのサイト内のグレン・ケスラー記者のプロフィールページ(スクリーンショットを筆者撮影)
政府機関や外交の取材を長年続けてきた経験をもとに、機転の利いた魅力的なファクトチェックを行い、フェイク情報の巧妙さや社会的な影響力の深刻さを「ピノキオマーク」の数でレーティングするなどの手法を編み出した人です。
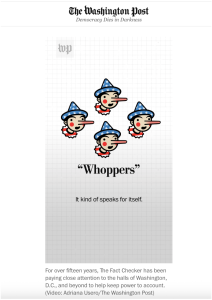
ワシントンポストのファクトチェックは、ピノキオのマークの数でレーティングしている。ピノキオ4つは「大ウソ」というランク。ウソを連発するとしてトランプ大統領には「無限ピノキオ」が付けられたこともある。
(レーティング説明の動画を筆者がスクリーンショット撮影)
「意見」をファクトチェックする
彼が中心となって行ったファクトチェックに、以下のようなものがあります。
President Trump’s repeated claim: ‘The greatest economy in the history of our country’
(トランプ大統領が繰り返す主張:「この国の歴史上 最高の経済状況」)
2018年9月7日

「わが国の経済は最高の状態だ!」というのは「個人的な意見」の表明であり、一見ファクトチェックにはそぐわないように思えます。
しかしトランプは、2018年6月から9月までの3カ月あまりの間に、同紙の集計によると40回以上も「史上最高の経済状況」という評価を強調してきたことがわかっています。
そしてこの記事はこのように述べています。
こんなに何回も繰り返されてしまった意見は、ある種の真実に変わってしまう恐れはないのだろうか?
大統領は3カ月間、この主張を言い続け、最後には自分の言葉を引用する形で「経済状況はわが国の歴史上最高の状態にあると言われている」とも言い出す始末である。
私たちは、この問題を検証しなければいけないようだ。(翻訳は筆者)
政治の世界では「ウソも繰り返すと真実になる」という言葉もあります。トランプの「誇大自己評価」が支持者に根拠のない勢いを与えたり、不支持の人たちも感情的な反論しか思いつかないのでは、かえって分断が深まってしまうという問題もあります。
権力を監視するというジャーナリズムの原則に照らせば、ファクトチェックの「掟破り」をしてでも、挑まなければならない偽・誤情報があり得るということです。
最大限に論理的検証を試みる
ケスラーは、まず「アメリカの歴史上最高の経済状況」という言説が、誰か他の人から発せられた可能性を探ります。
そこで、トランプがよく観ているフォックス・ニュースの2人のニュースアンカー、ルー・ダブスとショーン・ハニティが自分の番組で、トランプ政権下での経済を誉める発言をしていたかどうか、発言録を検証します。
その結果、2人のアンカーは、トランプが演説などで経済状況を自慢する発言をした際に、呼応してニュースとしてとりあげてコメントしたことは1回もないことを発見します。
また、それらの発言では「ここ10年」とか「この20年間」のような限定がついていたことも明らかにします。
2008年から2009年はリーマン・ショックでアメリカ経済が深刻に冷え込んでおり、比較することが妥当かどうかという指摘も忘れません。
「わが国の歴史始まって以来の」という評価は、少なくともニュースになるような情報として伝えられていないことを、まず明らかにします。
専門家も納得できる指標
次にこの記事では、「経済が最高の状態にある」と言うならば、当然満たしていなければならないはずの指標を検証します。
まず、「失業率」をチェックしてみると、2018年9月当時の失業率3.9%より、1951年も、1952年も、1953年も、1968年も2000年も低い水準であったということをデータで示します。
ケスラーは、トランプが失業率の議論をするときに意図的に混同してきた「労働参加率」についても、2018年の数字は1950〜60年代の水準に遠く及ばないことも指摘します。
適切な専門家の評価を加える
ケスラーは次に、経済を評価する一般的な指標である、GDP(国内総生産)の伸びについて比較分析します。2018年の第二四半期のGDP成長率は4.2%で、彼が公約として掲げた4%は上回っていたものの、第二四半期だけの成長率でも、トランプが大統領であった2017年通年の成長率を比べても、はるかに及ばない年が10年以上あることを突き止めます。
ケスラーは、これらの評価について、経済史などを専門にする大学教授やエコノミストからコメントを取り、そのうちの一人からは、「経済が好況かどうかはGDPでは判断できず、むしろ労働生産性(労働時間あたりの生産量の伸び)などを見るべきだが、トランプ政権時は1950〜60年代に比べてそんなに高い水準ではない」とのコメントを取ります。
100%とは言えませんが、合理的と思われるすべての可能性にあたって検証し、「ピノキオ3個(重大な事実誤認/明らかな矛盾)という4段階中深刻な方から2番目というファクトチェック記事として発表しています。
「奇妙なのはトランプが経済は史上最高だと主張する必要がないのに、していることだ」と結んでいます。
「権力監視」のマインド
このような事例で重視されるのは、「ファクトチェックとは何か」という形式論ではなく、権力が乱用されそうなら、「ちょっとおかしいんじゃない?」とフラグをあげるというジャーナリズム的な意識と、柔軟性だということです。
ワシントンポストの挑戦で、それではトランプ支持者と不支持の人の対話が促進されたかというと、事態はそんなに簡単ではありません。反発もかなり強かったと聞いています。しかし、ケスラーに迷いはありませんでした。
当時のトランプもそうでしたが、特定の政治的な主張を強調しようとする言説は得てして、一見、ファクトチェックが不可能に見える「意見を含む主張」の中に、「エビデンスにも見えるようなデータ」を紛れ混ませたりするものです。
そのような時に「データ」だけに注目して、せまいファクトチェックをするのではなく、「どのような深刻な政治的影響が発するのか」を判断し、社会的な文脈を考えてマクロにファクトチェックを行う意識をメディアには持ってほしいと期待します。
ニュースの消費者の私たちも、当然それを期待するという目で、報道を評価していきたいものだと思います。
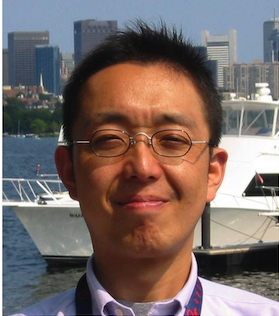
奥村 信幸(Okumura, Nobuyuki)
武蔵大学社会学部教授、FIJ理事
1964年生まれ。上智大学大学院修了(国際関係学修士)。1989年よりテレビ朝日で『ニュースステーション』ディレクター等を務める。米ジョンズホプキンス大学国際関係高等大学院ライシャワーセンター客員研究員、立命館大学教授を経て、2014年より現職。訳書に『インテリジェンス・ジャーナリズムー確かなニュースを見極めるための考え方と実践』(ビル・コヴァッチ著、トム・ローゼンスティール著、ミネルヴァ書房)。